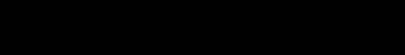=クライスラーの秘密 の詳細の目次(リンク)=
音色
運弓
リズムと歌い回し
暗譜力
練習法
品格
楽器
心に残る言葉
どれ程キャリアを重ねたヴァイオリニストにとっても、練習が不可欠であることはいうまでもありませんが、そのやり方は、演奏家それぞれで、まさに千差万別といったところでしょう。
練習法
フリッツ・クライスラーのとった、練習にたいする基本姿勢は、いろいろな意味で含蓄の深いものだと思われ、ご紹介する価値のあるものと思われます。
まず、クライスラーの言葉をそのまま、「フリッツ・クライスラー」から引用します。
いわく「本当の演奏家の才能は生来のもので、練習によって得られるものではありません。完成途上の演奏家の場合、技巧上の習得は若い時期の問題で、そのあとは、彼がヴァイオリンを弾く真の才能をもっているかぎり、ことさら楽器と取り組む必要はありません。」と。
さらに、若い修業時代はともかく、コンサートヴァイオリニストとして自立するほどのレベルに達すれば、必要な練習時間の長さは、単なる自己暗示の結果に過ぎない、とクライスラーは考えているようです。
そして、彼自身、自分には練習は必要ないのだと暗示をかけてきたお陰で、ほとんど練習はしなくても済んでいる。自分は、演奏中に技巧のことを気にかけたことはないし、もし、少しでも技巧のことが気になるようであれば、その曲を人前で弾くべきではない、とも言います。
「フリッツ・クライスラー」からは、あたかもその正しさを裏付けるような、対照的な二つの事例を見出すことができます。その一つはサラサーテの例、もう一つはクーベリックの例で、二人とも、パガニーニの再来といわれるほどのヴィルトゥオーソ(名人芸的演奏家)でした。
クライスラーは、おもにイギリスを拠点に活動していた若い時代、サラサーテとも頻繁な交流があったのですが、当時サラサーテは、たとえその晩に演奏会が控えていても、一日中、ヴァイオリンに触れることすらせず、そのまま平気でステージに上がり、しかも、たった今まで練習に励んでいたかのように、完璧に演奏したそうなのです。
クライスラーが、練習にたいする自己の信念を抱く上で、この偉大な先輩の感化を大いに受けたであろうことは、想像に難くありません。
一方、クーベリックは、たまたまある演奏会の直前、十二時間を超える練習を自らに課してステージに上がったのですが、「その晩の彼の演奏は技巧的には完璧でした。けれどもそれは中身のないもの(「フリッツ・クライスラー」から引用)」だったそうです。
また、クライスラーの主張によれば、ある曲を演奏するために、通常一般的に行われているように、技術的な練習ばかりを積み重ね、肉体的な一種の「慣れ」を味方に付けておこうとすると、もし何らかの原因でステージで神経過敏になり、筋肉間のバランスがくずれてしまうと、もはや自己制御は不可能で、結果はさんざんなものとなる。したがって、そのような事前の練習にどれ程長時間をかけても、つまりは時間の浪費に過ぎない、のです。
クライスラーが、演奏と練習の連携を、結局どのようにとらえていたかは、やはり「フリッツ・クライスラー」の記述をもとに整理すると、次のように言えるのではないでしょうか。
第一に、クライスラーは、演奏を、純粋に「頭脳」の問題としてとらえ、けっして「肉体(左手と右手)」の問題とは考えていません。
演奏は、ちょうどピストルを撃つようなものだと、彼は言います。
つまり、弾こうとするある楽句を認識し(的を見)、どう弾けばよいかを正確に頭の中で思いめぐらし(ねらいをすまし)、左手と右手に適切な予備指令を与え(指を引き金にかけ)、後はただ、実際に弾くという行動に移せば(わずかに力を加えれば)よいだけ、なのです。
「フリッツ・クライスラー」には、こうも述べられています。
いわく「演奏者は音符に火を点ずるまえに考えるのであって、音を出している最中や出し終わったあとだけではありません。彼の筋肉は身構え、心のなかには肉体的概念がまざまざと浮かび、そして意志の軽いひらめきで、彼の目的は達成されるのです。」と。
第二に、たとえ少々不確実なパッセージがあったとしても、それは臨機応変の機敏さでカバーするべきものであり、ステージ上で、完全に自分の力を出し切れるよう、集中力を維持することが必要である。演奏会直前の練習は、こうした「頭脳」の働きを鈍らせるだけでなく、かえって、最も大切な機敏さを殺しかねない、ことなのだそうです。
同じく「フリッツ・クライスラー」から引用しますと、さらにこういう表現もしています。
つまり、「私にとってもっとも必要なこと、もっとも望ましいことは、情熱を蓄えておくことであり、新鮮で軽快な演奏ができるような状態にあることです。私は近々弾くことになる曲をけっして練習しません。私はその曲を新鮮なままにしておく必要があるのです。その曲にあきてしまうようではいけません。何であれ曲を楽しまなければ、私は演奏できないのです。」と。
ただ、ここで、練習と技術的な完成度との関連について、少し別の観点から、付け加えておく必要があるかと思います。
ご承知のように、クライスラーよりやや遅れて登場したハイフェッツの、あの神のような技術的完全性と演奏のムラのなさは、じつに二十一世紀の今日でも、おそらく多くのヴァイオリニストにとって、理想であり続けている、といって過言ではないでしょう。
たしかに、ハイフェッツの出現の前と後では、演奏者はもちろんのこと聴衆の中においてさえも、演奏の技術的な完成度にたいする判断基準が、雲泥の差で、レベルアップしてしまったかのようです。
たとえば、かつてのヴィルトゥオーソの一人であったヴィエニャフスキは、その保有していた卓抜なる技巧にもかかわらず、曲の難しいパッセージの演奏に際しては、「一か八かやってみなくちゃならない(「ヴァイオリン演奏の技法」から引用)」、と考えていたのです。
それはつまり、クライスラーの成熟期にあっては、技術的な完璧性は、かならずしも演奏の至上命題ではなかった、ということです。
今日のように、優れたヴァイオリニストのすべてが粒ぞろいで、ムラのない技術的完成度に到達しているのは、ひとえに、ハイフェッツを渇仰し、彼に触発された、直接の影響ではないかと思われます。
少しでも「ハイフェッツ」のようになりたい、との一心で、技術的習得やより合理的な練習法が、かつてなかった程に模索され重んじられ、そしてその結果、平均的なヴァイオリニストの技術水準さえも、大幅に向上したのです。
それではもし、クライスラーの所有していたとされる技術レベルを、現代の到達レベルから評価したらどうなるか、という興味深い疑問については、どの文献でもほぼ、次のように結論が一致しているのです。
ここでは、「二十世紀の名ヴァイオリニスト」から引用しますが、その書物の著された四十年前ですら、
いわく「技術的な完全性という点では、彼と同時代の多くのヴァイオリニストたちが彼にまさっていた。イントネーションの精密さという点では、ほとんどすべてのヴァイオリニストが彼を凌いでいた。」と。
しかし、技術的な完全性への欲求や、その為に余儀なくされる長時間練習という、ヴァイオリン演奏界一般のこうした風潮に対して、これもやはり何十年も前から、ある懸念が表明されていたということも、また事実でした。
私には、その見解の是非を判定することはできませんが、ここにその一部をそのまま引用ご紹介して、ご参考に供し、皆さまのご判断を仰ぎたいと思います。
たとえば、フレッシュは、「ヴァイオリン演奏の技法」の中で、こう警告します。
いわく「ハイフェッツのような性質の最高度の精確さは、良心的な勉強の成果というよりは、むしろ特異な才能の結果だということを経験が教えてくれている。」と。
また、いわく「練習の質の方が練習時間自身よりももっと重要である。(中略)練習に捧げる時間が不十分だから、才能が伸びないのではなく、むしろ才能は過度の練習によって台無しにされるのである。(中略)芸術活動の両極、即ちメカニズムと芸術的精神は根本的には相反するものである。すべての機械的活動は、ある程度まで精神を殺し幻想を麻痺させる作用をする。」と。
また、ハルトナックは、「二十世紀の名ヴァイオリニスト」の中で、こう指摘します。
いわく「(前略)かけがえのない芸術家的個性は、今日(注:1960年代)では稀になってしまった。(中略)今日のヴァイオリニストの世代が技術的・芸術的な能力の拡大と引き替えに支払わなければならなかったものはまさに個人的な型ではなかろうか(後略)」と。
また、いわく「ハイフェッツにおいては技術的な完成と音楽的・美的観念があまりにも密接に結びあって」おり、ハイフェッツを模範とすることを好ましくない、としています。
そして、いわく「たいていのヴァイオリニストは本質的にハイフェッツのようなくっきりした個性に乏しいのである。技術の面でハイフェッツがなしたことは完成度の段階がきわめて高く、非常に才能をもった他のヴァイオリニストにとっても、彼に追随することはまったくの労力のむだに終わるであろう。」と。
さて、ふたたび、クライスラーのケースに話をもどしましょう。
とまれ、クライスラーの練習にたいする信念が、少なくとも彼に関する限り、まったく正しかったことは、次の二つの事例が、はっきりと証明しているでしょう。
その一つは、交通事故の後で、クライスラーがベッドの上で初めて楽器を奏でたときのこと。
一命を取りとめたとはいうものの、彼の身体も指も、もちろん良い調子どころではないのですが、久しぶりのヴァイオリンを手にして、内的な演奏への衝動は抑えきれないほど、高まっていたそうです。
そして、「私は自分にこう言い聞かせたのです。これは自分の指なのだ、私の奴隷なのだ、私は司令官なのだ。そして私は指たちに弾けと命令を下し、(中略)指は弾いてくれたのです。(「フリッツ・クライスラー」から引用)」と。
今ひとつは、クライスラーが、今日では信じられないほど、連日にわたり、しかも多彩なプログラムのコンサートをこなしたという、紛れもない事実です。
ある年などは、たった一年で、世界各地での二百六十回(アメリカだけでも百二十回)の演奏会を消化した、と伝えられます。
それらは、体力の問題もさることながら、ひとえに、彼の記憶力と、技術的練習にではなく「頭脳」のひらめきに依拠するという、彼の演奏法との、すばらしいコンビネーションがあればこそ、初めてなし得ることだったのではないでしょうか。