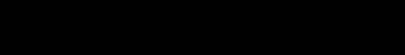=スウェデンボルグの詳細の目次(リンク)=
その生涯
思想の特徴
霊能の事例
その生涯(続き)
壮年期
幸い、エマニュエルが出版した「哲学・鉱物学論文集」は、ヨーロッパの多くの国で大好評でした。
この出版の翌年、父親イエスペルが亡くなり、さらにその翌1736年の初秋のこと、四十八歳のスウェデンボルグは、あいまいな理由づけのまま長期の休暇をとり、ひそかに解剖学を学ぶために、パリにおもむきます。この留学も、結果的には四年にもわたる、長期のものとなりました。
もともと、解剖学などは、当時のスウェーデンでの常識からすれば、何とも怪しげな科学というべきものであったうえ、鉱業の技術者である監査官の立場からも、まったく不要なものであるわけですから、もし留学の目的を、それとはっきり知る人がいたとしたら、これはまことに、首をひねらせられるような、おかしな行動だったに違いありません。
しかし、この時のスウェデンボルグの真の目的は、解剖学によって、霊魂と肉体の連携のメカニズムを、より科学的に解明したいというものであったようです。
どの時点からそのような興味がわき起こっていたのか、あるいは、どこにその必要性があったのかは、よく分かりませんが、この頃発表された彼のいくつかの小論文からも、すでに彼が、それまでの持てる知識を統合して、その問題にたいするある程度の理論をまとめ上げていたことが、はっきりと見てとれます。
スウェデンボルグは、そこで、おおむねをまとめれば、次のような主張をおこなっているのです。 つまり、
「霊魂は、単に想像だけの産物ではなく、ある"実体"であって、それは霊魂の法則なるものにしたがって動いている。ここで"実体"というのは、たとえば、磁気と同じようなものという意味で、人間は誰も、磁気を目に見たり、この手に触れることはできないけれども、間違いなくこの世には磁場があり、それを測定することもできる。つまり、そこにはたしかに、なんらかの法則の支配がある。もしこれと同じとすれば、おそらく霊魂にも、それなりの法則、性質や特性があるであろう。さらには、霊魂も磁気と同じように、完全に消滅すること、すなわち「死ぬ」ことはないであろう。」と。
彼は、その自分の仮説を証明する一つの手段として、まず解剖学に精通することの必要性を痛感したのだ、と思われます。
なお、このような霊魂説は、別にスウェデンボルグの完全な独創というものではありませんでした。その種の学説は、すでにずっと古来から、繰り返し発表されていたもので、それらの中でも、スウェデンボルグの今回の行動の直接の動機となったのは、1734年に触れたであろう、医学者ホフマンや、心理学者ウォルフの学説であったらしいとされています。
ただ、もしそこに、スウェデンボルグの独創性があったとすれば、それは、いかなる先入観にもとらわれず、彼が得意とする科学に立脚した目で、新たに核心に迫ろうと試みたこと、だったのではないでしょうか。彼の言葉を借りれば、象徴的に、こう述べられてもいるのです。いわく「もし、顕微鏡があれば、霊魂や霊の構造だって完全に見えるものかも知れない(「巨人・スウェデンボルグ伝」から引用)」と。
ともあれ、こうして留学を実現させた彼は、パリはもとよりイタリア各地で見聞を広め、研究に没頭し、最後にアムステルダムに滞在して、ここから「エコノミー("霊の世界の体制"とでもいう意味だそうです)」を出版したのです。彼が、一応の目的をはたしてスウェーデンに帰国したのは、1740年の晩秋、五十二歳のことなのでした。
ところで、この留学で、スウェデンボルグは、このような所期の成果とはまったく別の、もう一つ大きな、初めての体験にぶつかっています。
それは、まだ旅行のごく初め、「エコノミー」を執筆し始めた頃のことで、1736年8月にアムステルダムに宿をとっていた時のことだ、とされています。
彼は、その時急に、ある「光のビジョン」を見たのです。
その光は、彼にとっては、ちょうど、彼の考えや結論にたいする一種の賛同のしるしのように受け取れる種類のもので、大きさも色も輝きもさまざまではありましたが、まるで神からの救いの手が示現されたかのように、美しく喜ばしい光であったそうです。しかし、なぜその光が現れたのか、そして、それがどこから来たのかは分かりませんでした。
その「光」は、やがて、時々スウェデンボルグを訪れるようになり、さらに、晩年の彼をあまりにも有名にした、あの「霊との対話」の前には、必ずそれが現れるようになったといいます。
もしこれを、単なる幻覚ではないとして、現代の研究成果にもとづいて解釈するとすれば、次のように考えることはできるでしょう。つまり、たとえばヨガなどの実践おいても、精神を高度に集中し、かつ呼吸を止める
(訓練されたヨガの行者では、小一時間ほども止めたままでいることが可能といいます) と、色々な光が見えてくる、ものなのだそうです。
したがって、スウェデンボルグが、著作や思索に熱中するあまりに、無意識的に、そのような呼吸の状態に陥ってしまったということは、十分あり得ることだったかも知れません。
事実、後年、霊界と接触する際には、意識的にその呼吸停止の方法を活用した、と語っています。また、彼は、ずっと子供の頃、朝夕のお祈りの時に、この種の呼吸法を初めて知り、その後はおもに、ものごとを深く考える必要がある場合に、その方法を試みた、とも言っているのです。
さて、この光のビジョンに加えて、これもいつの頃からか不明ですが、スウェデンボルグは、「自分のこれからの出来事を教えてくれる夢」を見るようになった、と回想しています。これは、何年にもわたって体験させられたことで、物事が実際に起こるより以前に、夢の中でそれを知らされていた、というのです。
あまりに明晰な頭脳を持った、科学者としての彼は、それらの体験を、かえって自ら、理解や説明することができず、自分は、気が狂ったあるいは気が狂うのではないか、と長い間煩悶し、狂気のテストの方法すらいくつか考案して、「繊維について」という書物の中で、それの紹介までしています。ちなみに、1743年に刊行されたその本は、先の「エコノミー」の第三巻にあたり、人間の神経組織を科学的に解析した労作となっています。
そして、「エコノミー」以下の一連の論文は、さらに新しい研究結果を加えて再構成され、1744年春、著者五十六歳の時に、四巻ものの「霊魂の王国 (その内容については、彼の科学的思想の特徴の別項でも、少し触れてあります)」の名前で、刊行されました。じつにこれは、科学者としてのスウェデンボルグの、最後の著作ともなったのでした。
なお、スウェデンボルグは、この出版の準備などで、1743年夏から翌年にかけて、ふたたびオランダやイギリスのあちこちに滞在しているのですが、その前後
(正確には1743年7月~1744年10月) の、日々の自らの夢の内容を、赤裸々かつ詳細につづった、ある日記を残しています。
彼自身公表するつもりなどまったくなかったこの記録は、彼の死後、およそ百年ほどたって偶然に発見され、現在、「夢日記 (後述の 「霊界日記」 とは異なります)」 として知られているのです。この中では、彼の見た性的な夢さえも、ありのまま記述されており、スウェデンボルグの人格を、精神分析するためなどにも、今日大いに役立てられています。
しかしなにより、ちょうどこの時期を境として、それまでは科学技術者でのみあったスウェデンボルグが、霊能者あるいは霊界の探訪家へと、大変身をとげており、この日記は、その微妙な軌跡をたどる上での、またとない貴重な資料ともなっているのです。
この「夢日記」の時期、スウェデンボルグは、昼間は、友人たちとのこれ迄どおりのつきあいや、研究活動などで、ごく「ふつうの」生活を送っていたのですが、夜の眠りについてからは、なんとも説明のつかない奇妙な体験を、頻繁に重ねていたようです。
彼は、夜中、夢の中にいるともなく覚醒しているともなく、しかも「夢」での行動や状況をすべて、はっきりと自覚することができたので (その記録が、「夢日記」そのものなのですが)、自分でも、このような種類の眠りをどのように呼んだらよいか分からない、と書き記しています。
当然、彼の身体にも異常が起こっており、それはたとえば、これまでになく長い睡眠時間
(いつも十一時間くらいは眠ったそうです) であってみたり、原因不明の発汗や、身体の震えだったりしました。さらに、このような意識の状態の中で、あるいはその状態の後で、神秘的なエクスタシーともいえる、また特別な意識状態に入ることもあったそうです。
具体的には、異常な震えにおそわれた後で、大きな音が起こり、それとともに、ある来訪者が現れ、彼らにかかわりのあるいろいろなビジョンが現れる、というものでした。そのビジョンは、スウェデンボルグの表現によれば、たいてい「神の国」のありさまで、訪問者の中には、天使や聖人がおり、1743年のアムステルダムでの体験では、キリストその人すらもたしかに混じっていた、といいます。
さらには、1744年4月6日(~7日)の、オランダの町デルフトでのビジョンでは、現れた人物の「手」は、スウェデンボルグの手をきつく握った、と日記に書き留められています。「巨人・スウェデンボルグ伝」の記述をそのまま引用すれば、このようです。
いわく「同時に私は彼の胸にもたれ、顔と顔とを見合わせた。その顔はこれぞ聖なる者の顔と思われるもので、すべてが筆舌に尽くせなかった。そして、微笑んでいた。それで私は、生きていた時のキリストはそんな人物だったのだと信じた。(後略)」と。
私は、キリスト教徒ではありませんし、もちろん霊能者でもありません。さらに、記録として残された「夢日記」にしても、ごく断片的にしか読んでいません。したがって、スウェデンボルグのいう「神の国」やキリストのビジョンにしても、それを目の当たりにしたときの、彼が感じたであろう至福の想いのようなものを、そこへ自分を感情移入させることができません。また、自分自身の「感覚」として想像することすらも容易ではありません。つまり、それらが、どれ程、彼に深い意味を持ったかを、ほんとうの意味では、理解することができないのです。
しかし、私にも、これらのいろいろな体験こそが、スウェデンボルグにとって、科学よりは神学、あるいは理性よりは信仰の方に、次第に傾斜する大きなきっかけとなったであろうことは、おぼろげながら納得できるように思うのです。もちろん、彼の場合には、その一方を、完全に放棄することは、けっしてなかったでしょうけれども。
その後、彼の研究のテーマは、微妙に変化したようです。それは、これまでの「霊魂はどのような仕組みで動いているのか」ではなく、「そもそも霊魂はなぜ、またどのような目的で存在するものなのか」という方向への、視点の変化だったかも知れません。
また、彼の手法も、少しずつ変化しました。彼は、自らの狂気に対して、やはり一片の疑いを残しつつも、これらの奇妙な体験に、より沈潜していく道を選び、これまで以上に、意識的にビジョンを出現させるよう、試み始めたのです。
一方、彼の変化は、その著書として、すぐに具体的な形を取り始めていました。その書物は、1744年終わりころに完成したとされる、「神への賞讃とその愛」というものです。この中で、スウェデンボルグは、世界の創造とアダムとイブの創造を題材にして、それを、あくまで比喩的にではありますが、これまでの「聖書」とはまったく違った、独自の物語に組み替えている、とされます。
物語の中で、登場人物の言葉を借りて、また、きわめて象徴的な表現を用い、彼はこう述べます。
いわく「人間が生きているのは愛の生命ゆえであり、生命とは愛がそうであるのと同じような性質を持ったものなのだ。(「巨人・スウェデンボルグ伝」から引用)」と。そして、キリストとおぼしき人は、「愛それ自身」と呼ばれているそうです。後年、聖書を、「シンボリック」ないしは「霊的」に解釈しようとしたスウェデンボルグの萌芽が、すでにここには、はっきり見られるのです。
さて、スウェデンボルグは、「夢日記」の終わり近くでは、彼が踏みこんだその不思議な世界に、いろいろな種類の「霊魂」がいることが分かった、と書き記しました。それはつまり、彼がここで初めて、「霊界」なるものの実在を確信した、ということでもあったのでしょう。そして、「夢日記」はまもなく中絶することになりますが、やがて、もっと自発的ではっきりとした目的を持った、霊界の探訪旅行の記録である 「霊界日記」 が、書き始められることになるのです。これについては、彼の霊的思想の特徴の別項で、少し触れてあります。
(続く)