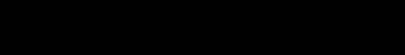=スウェデンボルグの詳細の目次(リンク)=
その生涯
思想の特徴
霊能の事例
思想の特徴(続き)
科学的思想の特徴(続き)
しかし、スウェデンボルグが生涯をつうじて持ちつづけた最大の疑問は、人間とは何かということでした。
とくに、若い頃の科学者としての彼がテーマとしたのは、霊魂というものがもし、よく言われるように死後も存在するものならば、おそらく物質ではない霊魂と、物質である肉体とは、どのように結びついているのか、ということだったのです。
それを、解剖学の手法で解き明かそうと試みた成果が、大著 「霊魂の王国 ( "生物界" とも訳されています)」 でした。ここでは、彼はとりわけ脳の働きに着目し、優れた洞察力によって、現在では大脳生理学として確立されている各種の理論に、ほぼ到達していたのでした。
たとえば、脳の表面の灰白質 (のち大脳皮質と呼ばれます) が精神活動で重要な役割を演じていること、この脳の表面と身体の各部は神経繊維でつながっていること、その実際のコントロールは、灰白質中の小さな卵形のもの
(のち神経細胞と呼ばれます) が行うこと、などを提唱しています。
他方、それと視点は異なりますが、当時一般的に信じられていた、人間の胎児は 「宿った」 時すでに人間の五体の形をもっている、という説をまったく否定してもいたそうです。これは、彼の求めている霊魂と肉体の関係を明らかにするうえでは、きわめて大切な前提ともなったものでした。
彼は、ひよこの例を借りて、このように説明します。
「卵の胚の中にはどんな種類の小さなひよこもいない、小さなひよこがそのまま大きくなるのではない、胚の中にあるのは<ある種の形成力をもった物質、あるいは形成力であり、それがひよこのいろいろな器官を一つ一つつくらせていくのだ>。(「巨人・スウェデンボルグ伝」から引用)」と。
そして続けて、このような意味のことを言います。
つまり、その形成力そのものは、最初は、卵の中の、混沌とした (カオス的な) ある種の液体的な物質の中に存在する。逆に見れば、その液体的な物質には、もともと生命または霊魂というべきものが宿っており、自分がどのように形成されていったらよいかを自分自身に示すような、完璧な設計図をも内にあわせ持っている。要するに、この形成力を、霊魂または生命と同じものと考えてもよい、ということなのです。ちなみに、この霊的な液体を、スウェデンボルグは、「動物霊」という言葉で表現している場合もあるようです。
さて、さらに、「巨人・スウェデンボルグ伝」から引用しますと、スウェデンボルグは、次のような考えに至ったようです。
つまり、まず設計図的なものを内に持っている以上、「生命とは目的や意図と関係しているもの」であり、生無きもの
(たとえば、石ころなどの物質をいいます) にたいして、「生あるものが霊魂によって意図的にコントロールされ」ているのみならず、「肉体は、霊魂が自分の目的のために織り上げた何かである」がゆえに、「いったん肉体がつくられると、肉体は霊魂と相互関係を持つようになる。しかし、霊魂のほうは製造者なので、相互関係だけでなく、肉体のメインテナンスをしたり、修復可能な限りは修復したりする役目も担う。」のであると。
また、ここで生命とか霊魂とかいうものは、時間や空間とは別の世界にある、物質の形を取らないエネルギーないし働きのようなもので、それがいったん我々の物質世界に
「流れこんだ (流入した)」
後では、神経繊維によって伝達され、形成力を実現しようとするのであろう、と。
では、その「流入」はどのように行われるのか、あるいは、その「流入」を引き起こす実体は何なのか、については、科学者としてのスウェデンボルグには、解答を見つけることができなかったようです。
そこで彼は、敬虔なキリスト教徒として、「流入」は「神」の行われる御わざである、と考えることで、いちおうの心の平安を得るしかなかったのです。その上で彼は、その仕組みを分析的論理的にこれ以上解明することは、人間にはできないように思う、とも告白しました。
しかし、その後の彼の変貌から振りかえるとき、彼はそこで解明をあきらめたのではなく、唯一の光明を、哲学と、その頃の彼が体験し始めていた神秘的なビジョンとの中に、見出そうと試み始めていたものかも知れません。
ともあれ、スウェデンボルグは、この「霊魂の王国」の段階では、次のように結論しました。
いわく「世界の物質的側面は非物質的な力から生まれ出たものである。生命あるものは非物質的な力から生まれ、生命を付与された。生命は生命の根源、あるいは神に基づくものである。(「巨人・スウェデンボルグ伝」から引用)」と。なお、ここでの「生命」は、霊魂とほぼ同じような意味で使用されているものと思われます。
霊魂がどのように流入するかについては、その結論を、まだはるか先に持ち越さなければならなかったとしても、いったん流入した霊魂が、どのように物質化するかについては、科学者スウェデンボルグは、すでに明快な理論に到達していたようです。
模式図的に、私の理解のおよぶ範囲で、ごく概略のみご紹介しますと、このようではないでしょうか。
1.まず霊魂がこの物質界に流入すると、第一番に理性的な心を作ろうとします。
霊魂には根源的に、良心や直感のような内在的な働きや、肉体を設計図通りに形成しようとする力が備わっていますが、物質界で自分の 「目的 (そのくわしいことは、この段階ではまだ分かっていません)」
を実現するためには、アシスタントとしての理性的な心が必要なのです。この理性的な心は、おもに理解や意思することをその役割とし、大脳皮質の中に具体化されて、そこを足場にしてさまざまな作業をします。
したがって、肉体的な意味では、大脳皮質こそが霊魂の場なのです。スウェデンボルグの言葉を借りれば、こうです。
いわく「そこに霊魂は、組織の中のもっとも高貴な組織を衣裳にまとって住んでいる。霊魂はここに座っていて、そこに起こってくる考えに客として応対する。この高級で高貴な場所がもっとも内奥の感覚中枢であり、そこは肉体の生命がそこに登り詰めて終わる境界域になっている。霊魂のエッセンスと考えるべき霊魂の生命が始まるのも、この境界域である。(「巨人・スウェデンボルグ伝」から引用)」と。
2.心と呼ばれるものにはもう一つ、大脳本体の中においおいと作られて、中程度の知性を持つようになる、低位の心もあります。
これは、感情や感覚的なものに影響されやすい、低次元の心でもあります。
霊魂が、理性的な心と低位の心の、どちらの心からもまったく独立した、しかもはっきりとその上位に位置するものであるのにたいして、二つある心の方はこのように、霊魂ともかかわりを持ち、そしてさらに、後から形成される肉体ともかかわりを持つものなのです。
ところで、人間が完成された (生まれた) 段階でも、心には、霊魂の持つ内在的な働き以外のものは何もなく、いわば白紙の状態になっています。しかし、やがて、肉体の各部所からの感覚的な伝達情報が、低位の心によって、想念
(考え) という形でまとめられ蓄積されていきます。それはたとえば、道徳的な考え (いわゆる、"良い心"とか"悪い心"とか表現される場合の、"心"です)
であっても、かならず後天的なものだ、ということを意味するのです。
3.これらの中枢となる脳の形成と併行して、そのほかの物質的な器官や、五感などの感覚が形成されます。
こうして出来あがった人間は、せんじつめれば、霊魂と肉体だけからできていることになります。しかも、スウェデンボルグによれば、ほんらい肉体の役割は、「感じ、外観をつくり、行動を生み、上位の生命が決めたところに従って動かされ、上位の生命の決めたものを実行し、意思し、望むことである。(「巨人・スウェデンボルグ伝」から引用)」のでした。
しかし、人間の肉体の行動は、理性的な心が持つ働きの一つでもある、意志というものによって、ある程度の選択の自由を認められているともいいます。
霊魂のアシスタントとしての理性的な心は、まず上からは霊魂の働きかけを受け、同時に下からは、低位の心からの働きかけを受け、常に二つの力の間で、いつもある種の葛藤状態にあるのですが、最終的にはその時々に、意志という形で、両方のバランスを取り、また矛盾を一つにまとめ上げ、それをもとに具体的な行動をとる、というわけなのです。
この自由意志があるために、人間は、かならずしも霊魂のほんらいの「目的」どおりには動かない、ともいえるかも知れません。
4.スウェデンボルグが指摘したことの中に、我々がまったく誤解している、感覚の仕組みというものがあります。
感覚については、ふつう、肉体の感覚器官である目とか耳とかが、外界からの刺激を受け、それを大脳の感覚中枢が感知する。したがって、肉体の消滅 (死) とともに、すべての感覚はなくなってしまう、というふうに理解されています。
しかし、スウェデンボルグの解剖学的な研究によれば、外界の刺激は、物質的な脳で感知されるのではなく、非物質的な霊魂が持つ 「内面的な感覚」 力のようなものに、直接それと認識されていることが、証明できるそうなのです。
したがって、まったく信じられないことですが、生前に持っているような感覚は、死後も残り続けます。
後になって、スウェデンボルグが霊の世界に足を踏み込んだ結果、このことは、次のような事例からも裏付けられました。つまり、霊界にやってきたばかりの新参の霊は、しばしば、自分が死んでしまっていることを素直に納得しない、というのです。というのも、彼らは、生きているとき以上に鋭敏な感覚を持っており、見たり聞いたり、触れて確かめることができ、したがって、自分がまだ
「肉体」 を持っていると錯覚してしまう、のがその理由なのだそうです。
スウェデンボルグは、この辺りのことを、このように説明しています。
いわく「なぜなら人間だった時にも、人間は肉体ゆえに触覚そのほかの感覚を持っていたのでなく、肉体のほうがその生命をそこから受けている肉体の中の霊魂ゆえに感覚を持っていたものだからだ・・・だから、肉体の死後にも同じ原理はそのまま続いている。そこで霊は、自分が間違いなく肉体の中にいると考えているが、その考えは最後にはなくなる。これは肉体の生を終えて他界にやってきたばかりの霊にだけある考えで、その考えが生まれる理由は、彼らの肉体的触覚にある。(「巨人・スウェデンボルグ伝」から引用)」と。
5.記憶や意識についても、スウェデンボルグは科学的に分析しており、たとえば意識には、通常意識と内的な意識 (後にベルグソンが潜在意識と呼んだものです) という、レベルの異なった二つの意識があることを、すでに述べています。
また、記憶についても、それが大脳皮質の中の、今でいう細胞群の中に起きる状態の変化であることを指摘し、肉体的な記憶と同時に、内的な意識に照応している内的な記憶もある、と主張します。
肉体的な記憶は、感覚器官からの刺激に依存する記憶で、肉体の生存のためには欠かせないものではありますが、死によって消滅したり、少なくとも死後、霊界での働きは受動的なものになるのだそうです。新参の霊は、まだ一部この記憶を残しており、それを頼りに、生きていたときと同じような姿に、自らを再生することさえできるといいます。
これにたいして、内的な記憶能力は、感覚器官によって 「焦点」 を合わされたもの、つまり意識的に注意を向けて取り込まれたものはいうにおよばず、周りをも含めて全体を、いわば 「写真的」 に記憶することができます。それどころか、さらにもっと深く、生きている時に人間が
「考え」、また 「経験」 したことのすべてを、完全にすみずみまで焼きこんで、記憶しているというものなのです。
そして、スウェデンボルグは、この記憶は、霊に属するものであるゆえに、もちろん消滅することはなく、しかも霊おのおのの持つ記憶 (「考え」や「経験」を含みます)
は、霊界の高等な霊にかかれば、まるで映画のような光
(ビジョン) として、眼前に再現させることができる、といっています。彼はこれを、「天の事跡簿」 とでも呼ぶべき性質のものだと位置づけ、事実、必要に応じて、新参の霊自身に、この世における所業の動かしがたい証拠として、それが表示されたケースを、いくつか書き留めているのです。スウェデンボルグによれば、それはまさしく、刑罰とすらいえるほどの光景であった、とのことです。
(続く)