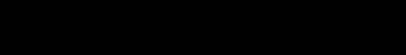=健康維持と病気予防の詳細の目次(リンク)=
目を大事にする
歯を大事にする
身体を大事にする
身体を大事にする(続き)
c)摂取するもの(続き)
2) 漢方薬
私は、昔から、どちらかというと漢方系の薬に興味を持ち、素人なりにいろいろ書物を読み、実際にもあれこれ試して来ました。
漢方薬といわれるもののなかには、健康の維持が目的のものが多数あります。もちろん、特定の病気の治療を目的とした薬は、症状に合わせて、専門医なり薬局なりで処方してもらわなければなりませんが、予防のためのこれらの薬の中には、ごく一般的に市販されているものもありますし、ちょっとした手間で、自分で作れるものもあります。
ここでは、そのごく一例として、クマ笹と薬酒を、ご紹介しましょう。
a. クマ笹
日本ではよく群生しているクマ笹には、なかなか捨てがたい薬効があるようです。
その中でも一番大きなものは、いま人気の、「血液サラサラ効果」 だといわれます。また、クマ笹には、このほか、ウィルスやガンなどにうち勝つための免疫機能の促進効果、身体の細胞を賦活させて各臓器の機能を高めてくれる効果、などもあります。
これらの薬理効果の詳細については、あとでご紹介する書籍などをお読みいただくか、下記の「日本サプリメント協会」 サイトなどを、ご参照ください。
このクマ笹を主成分にした漢方薬も販売されており、これは、クマ笹から抽出した青汁のエキスを顆粒状にしたもので、薬というよりはお茶の感覚で、溶かして、日に何度でも飲用するとよいそうです。
薄い塩味で香りもあり、飲み飽きないので、私としては、おすすめの商品です。
b. 薬酒
漢方系の薬酒として、比較的に入手が容易で、名がよく知られているものとしては、薬用養命酒と薬用陶陶酒があります。
その他、とくに中国のお酒などでは、一般の紹興酒 (老酒) などであっても、多かれ少なかれ、薬酒としての効用も含まれるといわれます。これは、食はすべて健康のためのもの
(この"医食同源"については、後述の 「食材の温冷作用」 の項もご参照ください)、というお国柄からして、当たり前かも知れません。
日本の薬酒の代表の一つ、薬用養命酒は、おもに漢方生薬
(高麗ニンジン、ケイヒ、インヨウカクなど) をベースにした、滋養強壮を効用とする、甘くて飲みやすい薬酒です。
一方、薬用陶陶酒は、おもに反鼻 ("はんぴ"は、マムシを乾燥させたものをいいます)
をベースにしたもので、甘辛各種のブレンドがあるようです。
どちらも、ドラッグストアや酒類のディスカウントショップなどで、広く販売されています。ただ、薬用陶陶酒については、製造元が最近倒産したと聞きますので、今後どのような供給状況になるのかは、よく分かりません。
こうした商品は、各種成分がバランス良く配合されており、安全性にも問題がないので、おすすめしますが、オリジナルの薬酒を作ることも、たいして難しくはありません。
以下に、私が、長い間にいろいろ試してみた、薬酒のあれこれを、ざっとご紹介してみました。いずれも、滋養強壮の効用を期待するためのものですが、即効性はなく、長い間飲み続けることで、徐々に効き目があらわれます。
なお、記憶があいまいな点もあり、使用材料の分量などはかなり適当ですから、ご注意ください。
また、抽出に要する期間も、用量によって一概にはいえませんが、着色するものでは、ある程度の濃さの色になれば大丈夫です。ニンニクや高麗ニンジンの場合には、着色はしませんが、二~三ヶ月後に少し飲んでみて、素材の香りがしっかり移っていれば大丈夫です。
その他、この種の薬酒の服用量は、とくにお断りしていない場合でも、一日30CCくらいまでが限度、とお考えいただきたいと思います。
1. シイタケ酒
ふつうの干しシイタケ適量 (大きさ中程度のもので十五個前後) を、35%のホワイトリカー (標準容量の一瓶分、1.8リットルを使用します。以下、とくに断りのない限り、このアルコール度数と分量になります)
につけるだけです。
シイタケのうまみが溶けこんで、独特の飲み味となります。
干しシイタケ農家では、商品にならない半端なクズを、このように酒につけこみ、常用しているために、風邪をひきにくいともいわれます。
2. ニンニク酒
新鮮なニンニク、中二個分くらいを、500~600CC程度のホワイトリカーにつけます。
ニンニクは生でつけてもよいのですが、成分をより速く抽出するためには、一度蒸してさましたものをつけ込むのがよいようです。ただし、あの独特の臭気が、しばらく台所に籠もることを我慢してください。
一日あたり、小さじ一杯くらいの分量を、好みの飲み物 (ジュースなど) 200CCに混ぜて、服用します。
3. 高麗ニンジン酒
高麗ニンジン150グラム程度を、ホワイトリカーにつけます。ニンジンの形のままでなく、こまかく切ってつけこめば、そのぶん速く成分が抽出されます。
高麗ニンジンは、乾燥させた市販のものを、漢方薬局などで購入しますが、薬としての即効性を期待するわけではありませんから、それほど上等で高価なものでなくてもかまいません。
上記のニンジンの用量ですと、一度抽出して飲みきったあと、また同じニンジンで、新しくホワイトリカーだけを追加すれば、二番煎じ酒にすることもできます。ただし、二番煎じは、抽出期間が、倍程度長くなることにご注意ください。最後に残ったニンジンそのものは、料理などに混ぜて食べてしまえば、無駄にはなりません。
高麗ニンジン酒は、疲れた時などにも、比較的速やかな効果があるようですが、高血圧の方などは、あまり常用されない方がよいと聞きます。
4. マムシ酒
当たり前のことですが、マムシは、あの形のままのものを使用するのではなく、反鼻 (商品としては、マムシの乾燥粉末) を使用します。反鼻一瓶 (ほぼ60グラムくらい)
の分量を、ホワイトリカーにつけますが、これだと、やや薄めかも知れません。
そのまま入れると、抽出液と粉末が混じって、服用する時の酒の濁りがいやだという方は、まず、目の細かい布製の袋に粉末を入れたものを丁寧に縫いあわせ、その袋全体を、ホワイトリカーの中に沈めます。私の経験では、コーヒーの抽出に用いるネルの袋
(中位の大きさのもの) を転用するのが、簡便です。
抽出後のマムシの粉末は、良質のタンパク質でもあるので、料理などに入れて使いきります。
5. イカリソウ酒/ナツメ酒
漢方生薬のイカリソウの葉 (市販の500グラム一袋の、四分の一程度) を、ホワイトリカーにつけます。イカリソウは、別名インヨウカクともいわれ、薬用養命酒にも、成分として含まれています。
イカリソウだけですと、いかにも野草じみた味で飲みにくいという方は、これも漢方生薬のナツメ (乾燥させた実) を十個ほど加えてやると、やや円やかになって飲みやすくなります。
このナツメは、それだけで別の薬酒を作ることもできます。ナツメ酒は、ナツメ (市販の500グラム一袋の、二分の一程度) を、ホワイトリカーにつけます。実の形のままでなく、こまかく切ってつけこめば、そのぶん速く成分が抽出されます。
6. クコ酒
漢方生薬のクコ (枸杞子"くこし"といって、乾燥させた実が市販されていますので、500グラム一袋の場合であれば、その三分の一程度) を、ホワイトリカーにつけます。クコは、一つ一つが小さな紅い実なので、更にこまかくする必要はありません。
比較的よく耳にする漢方生薬のわりには、値段が高く、正規メーカーのものは、500グラム一袋が二千五百円ほどします。ただ、もう少し安い商品を、スーパーのドライフルーツや種子を扱ったコーナーなどで見かけることもあり、そちらを使用される方法もありますが、両者の品質の相違などのくわしいことは、よく分かりません。
ご紹介書籍/サイト(外部リンク):
| 書名 | 著者 | 出版社/出版年次 |
| クマ笹の秘密 | 大泉和也著 杉靖三郎監修 |
健友館 1995年刊 ヘルスブックシリーズ |
ご紹介商品/サイト(外部リンク):
| 商品名 | サイト | 備 考 |
| ササグリン | 阪本漢方堂 | ただし、専用サイトではなく、お店の紹介ページになります |
| 薬用養命酒 | 養命酒製造 | |
| 薬用陶陶酒 | 陶陶酒本舗 | |
| 高麗ニンジン | 更生堂薬局 | 横浜中華街にある、水虫薬で有名な老舗の漢方薬局です。以下のサイトのトップページから、「店舗一覧」
> 「店名別か行」 とリンクをたどった所に、紹介情報があります 横浜チャイナタウン
|
| 赤マムシ粉末 | 阪本漢方堂 | 上記をご参照ください |
| 赤マムシ粉末 | 陶陶酒本舗 | 上記をご参照ください |
| 漢方生薬各種 | ウチダ和漢薬 | 漢方生薬のメーカーです |
ご紹介情報/サイト(外部リンク):
| 情報名 | サイト | 備 考 |
| サプリメントデータベース | 日本サプリメント協会 | 「症状から探す」、「素材から探す」、「メーカーから探す」、「製品名から探す」
の四種類の方法で、「サプリメントデータベース」
内を検索することができます (本文内の参照箇所へ戻る) |
(続く)