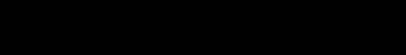=健康維持と病気予防の詳細の目次(リンク)=
目を大事にする
歯を大事にする
身体を大事にする
身体を大事にする(続き)
c)摂取するもの(続き)
5) 食材の温冷作用
ふだん、食事といえば、私たちは、自分の好きな食材を、食べたいときに好きなように調理して、何気なく済ませているわけですが、もし健康という観点で見るなら、献立をたてる上でも、食材を組合せる上でも、それなりのルールと知識が必要となります。
ここでは、おもに漢方の立場から、食材というものを、ちょっと考えてみたいと思います。
a. 漢方から見た食材
「医食同源」 という言葉があるように、中国では古来、ふだんの食事が、健康を維持する上でことのほか大切なものだ、と考えられてきました。こうした漢方の考え方を、実際の献立へ具体化するための基本として、体を温める食べ物と冷やす食べ物、という食材の性質の分類法があります。
その意図するところは、できるだけ健康面でプラスになるように、すべての食材の持つこの性質 (身体に与える作用) をうまく利用しつつ、体調にあわせて調理したものを食べよう、という点にあり、それらをさらに応用発展させたものが、いわゆる 「薬膳」 料理だといえます。
b. 身体によい食材
こんにち、物流システムが整備されたおかげで、季節を問わず、日本にいながらにして、世界各地のどんな食材も手に入れることができます。そしてそれが、かつてないグルメブームを支えているのかも知れません。
たしかに、少しでもおいしい物を食べたい、ふつうなら手に入らない珍しい物を食べたい、自分の好きな味覚のものだけを溢れるほどに食べたい、・・・というのは、人間として誰でもが、多かれ少なかれ持っている欲求なのでしょう。
しかし、もし健康ということを考えるならば、このような無鉄砲な食習慣は、かならずしも良い結果をもたらしません。人間の体調が、日々また季節に応じて微妙に変化する以上、本当をいえば、食材も、それにあわせて選択調理されなければならないからです。
たとえばかりに、願望のおもむくままに、特別なハウスで育てられた高価なスイカを、真冬に暖房の行き届いた部屋で食べたとします。それはそれで、ある意味、グルメなのかも知れません。
しかし、スイカは、春から夏へという自然の季節の推移の中で、時間をかけて育つからこそ、ほんらいの甘みやみずみずしさが、実のすみずみにまで凝縮されるのです。また、スイカは身体を冷やす食べ物だからこそ、夏に食べるのが最もおいしく、身体にも良いのです。
スイカに限らず、メロンやナシなどの身体を冷やすものを、わざわざ冬に食べたとしても、舌は満足するかも知れませんが、身体の受け入れ態勢の方は、果たしていかがなものなのでしょうか。
もしどうしてもというのであれば、これらの食材は、生ではなく、熱を加えて調理した状態のもの (加熱すると、ほんらいの性質が和らげられるといいます) を食べるようにしたいものです。
また、たとえば、風邪をひいて身体に水分を補給してやらなければいけない時、ショウガ湯やハチミツ湯などはよいのですが、熱い緑茶は好ましくありません。なぜなら、ショウガやハチミツは身体を温める作用をするのにたいして、緑茶ははっきりと、身体を冷やす食品だからです。
風邪治療の基本は身体を温めることなのですから、はやく治すためには、同じお茶でも、緑茶ではなく、むしろ紅茶を飲まなければならない道理になります。
c. 食材の温冷作用のあらまし
これら食材の温と冷の性質については、ごくおおざっぱにいえば、夏にとれる、トマトやキュウリやナスなどは身体を冷やし、冬にとれる、カボチャやネギなどは身体を温めます。
その意味では、野菜や果物だけでなく、「旬のもの」 というのは、豊富に出回って安いだけではなく、身体にとっても良い、じつに合理的な食材なのだといえます。
その他、南国育ちのバナナやパイナップルなどは身体を冷やし、北国育ちのサクランボなどは身体を温めます。ただ、同じ北国育ちでも、リンゴは、どちらかというと冷やす方の食材とされるなど、概して果物は、生のままでは身体を冷やす、と理解しておくのが無難なようです。
また、トウモロコシやサトイモやジャガイモなどのように、温冷の性質がさほど顕著でない、「平性」 と呼ばれる食材群もあります。
なお、食材によっては、どういう根拠によるものか、参照するいくつかの温冷表の間で、分類上のくいちがいが見られるようです。
そのいずれが正しいのかはよく分かりませんが、ここでの主旨は、食材ごとの 「温・冷・平」 の性質を明確にすることではありませんので、ごくアウトラインをご紹介するだけにとどめ、詳細は、薬膳のサイトなどをご参照いただきたいと思います。
ご紹介情報/サイト(外部リンク):
| 情報名 | サイト | 備 考 |
| 「食べ物の性質」 | 薬膳楼 | サイトのトップページから、「薬膳入門」
> 「薬膳の用い方(相性)」 とリンクをたどった所に、記載があります
|
| 「医食同源の極意」 | 程一彦/ 医食同源のススメ |
サイトのトップページから、すぐにリンクして記載があります
|
| 「中国四千年食文化」 | 薬膳 | サイトのトップページから、すぐにリンクして記載があります
|
| 「Kei.co.薬膳とは」 | ケイコの薬膳ワールド | サイトのトップページからクリックで入ると、すぐにリンクして記載があります
|
| 「漢方・薬膳レシピ」 | シーちゃん先生の 元気になろうよ |
サイトのトップページから、「中国の知恵」
とリンクをたどった所に、記載があります
|
| 「薬膳クッキング」 | 「はいから」オンライン | サイトのトップページから、すぐにリンクして記載があります |
(続く)