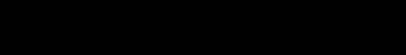=健康維持と病気予防の詳細の目次(リンク)=
目を大事にする
歯を大事にする
身体を大事にする
身体を大事にする(続き)
d)風邪の予防
よく 「風邪は万病のもと」 といわれますが、これは、ただの風邪でもこじらせると、いろいろとむつかしい病気に進展しますよ、という意味なのでしょう。
けれど同時に、一見風邪にようにみえていても、じつは単なる風邪ではなく、重大な疾病の初期症状であるかも知れませんよ、という意味もこめられているようです。
後者については、次の 「病気の予備知識」 の項で少し触れさせていただくとして、ここでは、いわゆる 「風邪」 の予防についてだけ、取り上げてみましょう。
ちょっとした鼻カゼ程度のものを含めれば、どんなに体力に自信のある方や若い方であっても、一年に数回は風邪をひく、といわれます。それほど、風邪はありふれた病気であり、季節の変わり目だとか、ちょっと疲れがたまったときとかに、あっと気づいたときには、もうひいてしまっているものなのです。
しかしそれでも、なるべく風邪をひかないに越したことはなく、そのための、ふだんからの注意などをいくつか、ご紹介します。
1) 手洗いとうがい
基本中の基本は、外出後の手洗いとうがいで、なかでも手洗いは、予防上、意外と馬鹿になりません。
かりに人混みに外出したとしても、風邪のウィルスが、口や鼻の奥深くまで一気に入り込むことは、それほど多くはないでしょう。それよりも、手先についたバイ菌を、自分で気づかずに、わざわざ口や鼻に運んでしまっていることが多いものです。
したがって、外出から戻ったら何よりもまず、手を、流れる水道水で、しっかりと、少し長めに30秒ほどかけて、洗います。
そのあと、うがいも必ず、励行します。うがいには、市販のうがい薬 (イソジンうがい液など) を使用しますが、手もとに常備されていない場合など、手っ取り早くは、緑茶 (あるいは紅茶でも同じです) でうがいをするのがおすすめです。
緑茶には、抗菌作用が強いカテキンが含まれており、それがウィルスを殺菌してくれるとともに、栄養成分であるビタミンCからは直接、風邪の治療効果を期待することもできます。うがいに使用するお茶は、「出がらし」 であってもかまいません。
2) 皮膚の鍛錬
昔から、風邪の予防に皮膚の鍛錬が有効であることは、よくいわれてきましたが、乾布摩擦や冷水摩擦は、その代表的なものです。ただ、乾布摩擦は、多少中途半端なので、どうせやるなら冷水摩擦をおすすめします。
しかし、なにも極端なことを実行する必要はありません。手始めには、風呂から出るときに、上がり湯のかわりに真水 (水道水) に浸したタオルを固くしぼって、いくぶん強めにこするように、濡れた身体全体の水気を拭き取ってやればよいのです。最後に、その残りの冷水は、両膝下から足先にかけて、ゆっくりと注ぎかけます。これだけで、身体の皮膚は、知らず知らずのうちに強化されていくでしょう。
また、夏の暑いさかりであれば、風呂から上がる際の冷水摩擦の代わりに、洗面器やシャワーから真水を直接、身体に浴びるやり方もあります。もちろん、最初は、心臓から遠い足先や前腕などにかけるところから始め、少しずつ全身に水を浴びるようにするのですが。夏の間のこのような鍛錬も、冬場に風邪をひきにくくするには、大いに役立つものです。
もし、銭湯を利用されている場合や、とくに温泉などに行かれた場合には、次のような入浴法も効果的です。
それはまず、熱い湯船にしっかり浸かって、十分身体が温まったところで、今度は洗い場で、最初は冷水摩擦を二三度おこないます。ある程度身体が順応してきたら、ぬるめのシャワーに切り替え、まんべんなく全身に湯をかけながら、次に少しずつ湯の温度を下げて、最後は完全な真水にします。そこで、もう一度、熱い湯船に浸かります。この手順を三、四回繰りかえすと、身体は芯から温まって、外がどんなに寒くても、家 (部屋) に帰るまで身体はポカポカしていることでしょう。これらも、皮膚のよい鍛錬になります。
3) 室温の管理
上記の皮膚の鍛錬に関係して、とくに自宅などの居住空間の室温なども、冬は低めに、夏は高めに、管理するとよいと思います。つまり、戸外気温との差がありすぎることが、身体の正常な体温調節を狂わせ、ひいては、風邪をひきやすくする可能性があるからです。
エアコンで精確な室温調節ができるのであれば、たとえば、冬は20度程度、夏は28度程度に設定するのがよいのではないでしょうか。この時、エアコンと平行して活用したいのが、今はあまり使われなくなった扇風機です。
冬は、風が直接身体にあたらないようにした上で、扇風機を
「弱」 くらいの回転で回しておくと、部屋の中の暖められた空気を適度に対流させるので、実際の室温以上に暖かく感ずるものです。それでも寒いようであれば、一枚よぶんに厚着をするか、場合によってはマフラーなどを併用します。
夏は逆に、風が身体に当たってもかまいませんので、やはり 「弱」 くらいで回しておくことで、実際の室温よりはるかに涼しく感じることができます。
本当は、夏の場合には、エアコンも扇風機もまったく使用せず、窓を全開にして、自然の風だけから涼をとるのが、最も身体への負担は少なく、したがって夏バテなどを招かなくてすむように思われます。その際、すべての窓をずっと開け放しておくのではなく、陽の直射や照り返しがあたる時間帯の窓側は、むしろ雨戸をしめて日差しを遮ったり、また簾をかけてやることだけでも、ずいぶん暑気をおさえることができます。
一般的に、あまり都会的な便利さに頼りすぎることは、かえって身体の順応機能を弱めてしまいますので、夏はそこそこ暑く冬はある程度寒いという、ほんらいの自然に近い状態にふだんの身体を慣れさせてやることも、風邪予防には有効だと思われます。
4) 冬の外出着
真冬に外出するときの服装では、次のことに注意します。
それは、コートは厚手の暖かいものを着るかわりに、その内側の服装はなるべく薄着にする、ということです。
こんにち、エアコンの普及で、ビルの中にしろ電車の車中にしろ、暖かすぎることはあっても、寒いということはまずありません。つまり、部屋の中の暖かさのせいで気づかぬうちにかいてしまった汗が、寒い戸外に出たとたん急に冷え、それが元で風邪をひいてしまうことが、けっこうあるように考えられます。
したがって、内側の服装をなるべく薄着にすることが、室内で汗をかくことの予防として大切なのです。上側のコートは、いくらでも着脱して臨機の調節ができますが、内側に一度着込んでしまった衣服は、外出先では、思うようには取り替えられないものです。
5) 首と肩の保温
背中や肩がゾクゾクしたら、まもなく風邪をひいてしまった、などということは、きっと皆さまどなたもおありのことだと思いますが、たしかに、肩先や首を冷やすことは好ましいことではありません。反対に、この近辺を暖かく保温してあげることで、風邪を予防することもできるだろうと思われます。
また、とくに首には、身体全体をコントロールする脳へ通ずる血管や神経が、比較的浅いところを通過していますので、風邪ばかりではなく他の病気の予防のためにも、なるべく冷やさないようにすることが望ましいのです。
そこで、冬場の寒さから首を保護するには、たとえばマフラーやタートルネックのセーターを、積極的に利用します。私などは、真冬で日差しの少ないような日には、室内でもマフラーを欠かしませんが、そのせいか、以前ほど風邪をひかなくてすんでいるようです。
また、睡眠中、肩先が布団や毛布からはみ出して冷やされることがないよう、首から肩先全体を巻き込めるような、少し厚手のバスタオルのようなものを、寝間着やパジャマの下に着込むというのも、風邪の予防には効果があるようです。バスタオルなどの代わりに、本格的な 「かいまき」 を使用されてもかまいません。
6) 湿度の管理
風邪は、一般的に、冬の晴れて乾燥した時期に流行るといわれます。
これは、ウィルスの活動が活発になるためなのですが、逆に、風邪のウィルスは、高温多湿な状態には弱く、とくに湿度が50%にもなれば、大半が死滅してしまうのだそうです。このため、室温のコントロール以上に、部屋の湿度を高めに保ってやることは、風邪の予防にたいしても、大きな効果があるのです。
わざわざ加湿器などを設置しなくても、室内に手軽に湿り気を与えるやり方として、部屋のどこか窓際や壁際などに、夏も冬も朝一番に、濡れ手ぬぐい一枚をぶら下げておくことを、おすすめいたします。
それでほぼ一日、そこそこの湿度を保つことができますし、同時に、埃に混じった風邪などのウィルスが、この手ぬぐいに吸着させられてしまうようです。というのも、こうして使用した手ぬぐいは、何ヶ月かたつと、まるでカビがはえたように部分的に真っ黒になってしまうからです。
むろん、手ぬぐいは、ある程度使用したら、よく洗濯するか、清潔なものと取り替えます。
ご紹介商品/サイト(外部リンク):
| 商品名 | サイト | 備 考 |
| イソジンうがい薬250ml | 明治製菓 |
ご紹介情報/サイト(外部リンク):
| 情報名 | サイト | 備 考 |
| 「風邪について (予防法~対処法)」 |
健康情報.jp | サイトのトップページから、すぐにリンクして記載があります
|
| 「たかが風邪、されど風邪」 | Dr赤ひげ.COM | サイトのトップページから、「家族の健康」
> 「シニアの健康」 とリンクをたどった所に、記載があります
|
| 「緑茶のヘルシーパワー」 | 京都府茶協同組合 | サイトのトップページから、「宇治茶のことを詳しく知りたい方は」 とリンクをたどり、ジャンプメニューから選択した所に、記載があります |
(続く)