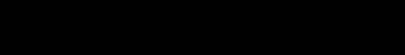=ケイシーの詳細の目次(リンク)=
その生涯
リーディングの特徴
リーディングの事例
リーディングの特徴(続き)
転生の問題は、ケイシー・リーディングの最も大きな特徴であるといえます。
しかも、リーディングによってもたらされる以上、ケイシーにとって、転生は、一つの思想ではなく紛れもない事実そのもの、でした。
では、なぜ転生があるのかについて、ケイシーは、どのように理解しようとしたのでしょうか。
ここでは、「私は前世の秘密を知った」などから引用整理して、私なりに、ご紹介してみたいと思います。キリスト教的な彼の考えを、ひょっとして十分把握できていない面もあるかも知れませんが、概要は、このようなものではないでしょうか。
まず、根本的に、この世の物質的な生身の人間の内には、霊魂 ("霊体"、"実体"などと呼ばれているときもあります)
が存在しており、これは、肉体が滅んだ後も、いつまでも生き続けるものだ、と彼は言います。
ごく大雑把にとらえれば、霊魂とは、人間の持つ本性のようなもので、過去生から引き継がれたこの世における所業によって、浄化もされれば堕落もするものなのです。
ところでもともと、すべての人間はその昔、神 (ここでいう神はまた、"宇宙の創造力"ないし"創造的なエネルギー"と呼ばれている場合もあるようです)
が創造した霊魂を持ってこの世に生まれたものであるため、その本性も、根元的には「神」にも近づきうるほどのものでした。しかし、人間は、同時に与えられた自由意志を濫用して、自ら道を誤り
(堕落し)、そこから、個人だけではなく、すべての人類の苦しみや悲しみが生じることになりました。
それでも、神は、それですぐさま人間を罰したり (たとえば、無限の地獄に落としたりすることです)、ましてや葬り去ったり (人類を滅亡させることです)
などはせず、むしろ、人間が、自分の自由意志によって自分を浄化する、という救済手段を残しておいたのです。そして、転生こそは、霊魂の浄化や霊的進化のために、われわれに用意された神の恩寵、ともいえるものなのです。
つまり、人間が、神に近かったかつての本性に戻るための修練の場こそ、過去世・現世・来世それぞれの生における、異なった人生行路であるともいえるでしょう。
そして、転生の間を結びつけているものが、カルマといわれるものなのです。
カルマは、もとはサンスクリット語の 「行為」 のことだそうですが、通常は、道徳的な面での作用反作用の法則、つまり因果律の意味で使われています。したがって、分かり易くいえば、過去生におこなった所業の貸し借りを、プラスの意味でもマイナスの意味でも、今生で清算しなければならない、ということになります。
ケイシーは、このカルマが、潜在意識のような深いレベルで霊魂に保存され受け継がれていく、一種の記憶のようなものだ、とも考えていたようです。
また、多くのリーディングから判断して、直前の生のカルマがすぐ次の生に引き継がれるとは限らず、数代前の過去生のカルマを今生に引き継ぐこともあるといいます。
それはなぜかというと、その霊魂が、過去生から、たとえどれほど重いマイナスのカルマを引き継いだとしても、新しい生で負荷される苦しみは、その人物の能力に応じた範囲内のものとなっており、背負いきれないほどのカルマに、霊魂
(存在体としての人間) そのものが押しつぶされるようなことには、なっていないからなのです。
清算されないカルマはさらに、後の生へと、持ち越されます。
こうして、一度発生したカルマは、人間としての転生が続くかぎり、けっして消えることはありません。そしてその意味では、どの生における良い宿命も悪い宿命も、すべては、霊魂自身が作ったもの、あるいは、霊魂自身に内在されているもの、ということができるでしょう。
ただ、その宿命よりも強いものが人間の自由意志であると、ケイシーが認識していたことは、「ケイシーの生涯-後期」で、ラマースからホロスコープについての質問を受けたことにたいする回答をご紹介した項でも、少し触れさせていただいたところです。
また、その自由意志こそが、霊魂の浄化を可能にする唯一の手段であることも、同様に忘れてはならないことであろう、と思われます。
参考文献(外部リンク):
| 書名 | 著者/訳者 | 出版社/出版年次 |
| 転生の秘密 | ジナ・サーミナラ著 多賀瑛訳 |
たま出版 1987年 |
| 私は前世の秘密を知った (エドガー・ケイシー 転生の証明) |
ノエル・ラングレイ著 今村光一訳 |
中央アート出版社 1986年 |
| 前世を記憶する 20人の子供 |
イアン・スティーヴンソン著 今村光一訳 |
叢文社 1980年 |
| 輪廻体験 (過去世を見た 人々の証言) |
「ヴェンチャー・インウォード」 (ARE機関誌) 掲載記事から 片桐すみ子編訳 |
人文書院 1991年 |
| 世界不思議百科 | コリン・ウィルソン& ダモン・ウィルソン著 関口篤訳 |
青土社 1992年 |