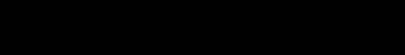=ノストラダムスの詳細の目次(リンク)=
その生涯
諸世紀の特徴
予言の事例
諸世紀の特徴(続き)
予言が、ノストラダムスの霊視によるものであったことは、「アンリ二世への手紙」の中の、次の言葉からはっきりとしています。
いわく「予言には何事をも混合せずに記述したのであります。たいていは天体の運行と結びついていて、レンズで見るがごとく、まずぼんやりとした視野に大きな悲しい事件や、英雄の陥落といった驚異的な悲惨な事件が見え、そして神の神殿の上に見え、次に地上の様子が如実にあらわれ、ついには、これらの事件とともに近づく時のしるしが知らされるのであります。(「大予言者ノストラダムスの謎」から引用)」と。
予言が、人類に明るい希望を持たせるものではなく、おおむね、悲惨な将来を予期させるものであることも、一つの特徴なのでしょう。
これは、個人にかかわるノストラダムスの予言の中には、輝かしい未来を告げたものもあったことから考えると、いささか不思議なことといえるでしょう。
そのような明るい予言として、たとえば、ノストラダムスはサロンに定住した翌年、1548年にイタリアに旅行に出かけていますが、その途中、一人の若い修道士とすれ違います。彼は突然、その初対面の青年の前にひざまづき、こう言ったのです。「あなたは、いずれローマ教皇になられるでしょう」と。
おそらく、若者の姿を目にしながら、ほとんど瞬時の霊視によって、その未来を確信した結果だったのでしょうが、通りかかった人々は、このありさまを見て、大いにあざけり笑ったそうです。なぜなら、このジョセフ・ペレッティは、もとは貧しい羊飼いで、しかも、なったばかりの修道士に過ぎなかったからです。しかし、予言通り、若者はまさしく教皇シクストゥス五世となったのであり、それは、ノストラダムスの死後二十年ほどしてからのことでした。
このほかにも、ほほえましい予言のエピソードは、いくつか伝えられています。しかし、そうした個人を離れた、人類ぜんたいの未来の予知では、そのように平和な何気ない情景以上に、ドラマチックでもあり激しくもある転変のありさまの方が、ひょっとするとより強く霊視のアンテナに働きかけてきた、のであるのかも知れません。
予言の範囲については、これも「セザールへの手紙」の中で明記されています。
いわく「私は予言集をやや解し難く推敲しようとしたが、それは今日から3797年までの絶えざる予言から成っている。(「大予言者ノストラダムスの謎」から引用)」と。
これは、ふつう、西暦年号であろうと考えられており、もしそうだとすれば、やはりこの点からも、1999年段階での世界滅亡は、あり得なくなるのです。
しかし、手紙の別の箇所では、次のような表現があり、この一見ずっと遠い将来とも思われる数字が、実際の年号とどのようにかかわりを持つのかは、よく分かりません。
同じ文献からさらに引用しますと、こうです。
いわく「天空の、目に見える判断について言うと、私たちは今すべてを終息させる7000年代にいるけれども、8000年代に近づいてもいるのだ。そのとき、広大な次元にある第八番目の天球をもつ天空となり、そこで、偉大な永遠の神が変革を仕上げ、星座群は自らの運動と、地球を揺ぎない安定したものにする超越的な運動とを再開するだろう。」と。
この内容は、私などにはなかなか理解しがたいところですが、少なくとも、ノストラダムスが生きた1500年代は、7000年代後半のある一点とも捉えられていたことが分かり、同じ手紙の中に現れた、さきほどの3797年との関連も、ますますよく分からなくなるのです。
なお、この文中で、「第八番目の天球をもつ天空・・・」とあるのは、ちょっと面白い部分かも知れません。
それはどうしてかといいますと、もともと西洋の占星術は、地球自身はおいて、太陽と月と「五つ」の惑星(水星、金星、火星、木星、土星)の配置にもとづいて作られたものなのだそうです。したがって、占星術師でもあったノストラダムスが、天球を表現するのに、かりに太陽と月までをも含めたとして「七つ」と表現するのならば、まだしも頷けるのですが、なぜか彼は、ここで「八つ」と言うのです。これは、単なる彼の勘違いだけのものなのでしょうか。
それともひょっとして、彼は、いかなる方法によるものか、当時はまだその存在すらも知られていなかった次の星、つまり天王星
(望遠鏡による天王星の発見は、1781年のことだそうです) の存在を、すでに予測していたのではないのでしょうか。もちろん、あくまでこれは、想像の域を超えるものではありませんけれども。
ちなみに、天王星に続いて、海王星、冥王星が発見されたことにより、現代の占星術は、太陽と月と「八つ」の惑星の配置によって、再構成されていると、聞いております。
つまり、もし太陽と月を別格であるとするならば、ノストラダムスの予言した、まさに「第八番目の天球をもつ天空」そのものとなっているのです。
-追記 (06年08月28日) -
ご存じのように、さきの2006年8月24日、国際天文学連合の総会において、「冥王星」は、準惑星 (じゅんわくせい→日本語での推奨の表記による) と再定義され、これまでの惑星から降格されることになりました。それは、純粋に科学的な論拠による、これからの新しい基準にもとづいた決定なのでした。
しかし、その一方で、現代の占星術は、構造上の少なからぬ自己矛盾を抱えこんでしまったのかも知れません。というのも、占いの手順の原則において、これまで「八つ」を基準のセットとしていた「惑星」という要素が、急に、正式な「七つ」とプラスアルファになってしまったのですから。
また、上でお話ししたような、「セザールへの手紙」の中の「第八番目の天球をもつ天空」という箇所にたいする私なりの解釈も、あまりにうがち過ぎた見方というべきで、今となってはいささか、ノストラダムスへの「ひいきの引き倒し」のような感が否めないでしょう。
もちろん、「冥王星」なる天球は、そのままずっと存在し続けるわけですから、このような再定義の後であっても、それが占星術に及ぼす影響力にはなんら変わりがない、との見方もあるでしょう。それも、もっともな意見です。
しかし、遠い冥王星ですらそれほど大きな影響力を持つのならば、似たような大きさをもち、しかも地球にはるかに近い、「セレス (火星と木星の間に存在し、ケレスとも呼ばれます。十九世紀初頭に発見され、太陽系の小惑星帯のうち最大級のものの一つとされます。これも、今回、準惑星と分類されました)
」という天球の影響などは、いったいどのように考えられるべきものだろうか、などという素朴な疑問も、また新たに浮かんできてしまうのです。
このような現代占星術のはらむ問題点は、「科学」の発達につれて、今後もかならず、形を変えて現れてくるのではないでしょうか。
ただ、お話をノストラダムスにもどした場合、彼に矛盾は、少しもありません。なぜなら、彼は、当時のだれもが目で見ることができる「星」をもとに占い、なおかつ、驚くべき的中率を得ていたのですから。
もっとも、彼が、そのたぐいまれなる洞察力によって、だれも思い及ばない、ある特別な「星」ないし「天球」の影響をも、その判断のよりどころにしていたのかどうかまでは、残念ながら、うかがい知ることのできないところですが。
参考文献(外部リンク):
| 書名 | 著者/訳者 | 出版社/出版年次 |
| ノストラダムス大予言原典 (諸世紀) |
ミカエル・ノストラダムス著 大乗和子訳 |
たま出版 1991年 |